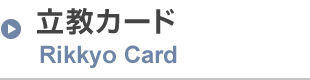Alumni Special Interview
女優 南沢 奈央さん 特別インタビュー
演じること、読むこと、書くこと、落語 すべてを糧に表現し続けていきたい。
女優 南沢 奈央さん(平25映身)

ドラマ、映画、舞台、ラジオMC、執筆など、多才な活躍を見せる女優の南沢奈央さんにお話を伺いました。
仕事に活きる学びを求めて映像身体学科へ
池袋キャンパスを訪れるのは何年ぶりでしょう。緑のツタに赤いレンガ、美しい風景は変わりませんね。
私が4年間を過ごしたのは新座キャンパスですが、私の両親も立教大学の出身で、しかもこの池袋キャンパスで出会っているんです。大学の雰囲気や建物がどんなに素敵か、そこでの時間がどれほど素晴らしいものだったか、2人にずっと聞かされていたので、立教には昔から憧れのような感情を抱いていました。高校生になって大学受験を考え始めたときも、まず頭に浮かんだのは立教です。その頃すでに女優の仕事をしていたので、大学に行くなら仕事にも生きることを学びたい。そう思って進学先を探していたところ、目に留まったのが現代心理学部の映像身体学科でした。映像制作、ダンス、演劇、いろいろな表現を学べると知って「こんな面白そうな学科があるんだ」と迷わず選択しました。
演じる以外の体験がその後大きなプラスに
仕事をしながらの大学生活だったので時間のやりくりは大変でしたが、キャンパスライフはしっかり楽しんでいましたよ。どんなに仕事が忙しいときでも大学に行くといつも仲間がいて、それぞれ自分が表現したいものに情熱をもって取り組んでいて、授業もどれを履修しようか迷ってしまうほど興味を惹かれるものが多くて、毎日が本当に楽しかった。仕事と大学どちらか1つではなく両方あったからこそ、時間にも心にもメリハリがついて濃密な4年間を過ごせた気がします。キャンパスにいること自体好きだったので、中庭でお弁当を食べたり、ホッとしたいときはチャペルに行ってみたり、あと、図書館にもよく足を運んで台本を覚えたりしていました。
授業で印象に残っているのは映像系のワークショップです。チームでミュージックビデオを制作したときは、コンテ、小道具、照明、撮影、編集と、あらゆる役割を経験できました。別の授業ではドキュメンタリー作品を1人で制作したこともあります。テーマを「自分」に決めて、子どもの頃からお世話になってきた方々を訪ねてインタビューを撮影し、第三者の視点から私という人間を客観的に捉える企画です。それまで仕事で「演じる」こと以外したことがなかったので、ほかの表現の手法や仕事を体験できたことは、その後の自分にとって大きなプラスになりました。ドラマも映画も舞台も1人では決してできない、大勢の人の力で成り立っているんですよね。それを痛感して、演じるということをいろいろな角度から見つめられるようになりました。
意外性が映像の面白さ 生の反応が舞台の醍醐味
同じお芝居でも、舞台と映像では大きく違います。私はデビューして10年ほど映像をメインに活動していたんですが、そこで感じたのは、同じお芝居をしてもどう切り取られるかで見え方が変わってくるということです。演技していたときにはわからなかったことが編集された映像から見えてきたり、そこに音楽が加わると世界観が一変したり、「こうなるんだ!」という意外性が毎回あって、そこが映像の面白さだと思います。短い稽古時間で作りあげなくてはいけないので、現場で生まれる演技やアイデアという瞬発的な要素も大事です。
一方で舞台は稽古期間が1カ月ほどあって、そこから本番を迎えて公演が終わるまで長いと3カ月くらい、同じメンバーで同じことを何十回も繰り返すという世界。稽古に時間をかけられるので、このやり方でやってみよう、やっぱり違うかな、じゃあこっちは?と、本番までに試行錯誤する余地があります。それから、お客さまの反応を生で受け取れる点も舞台の醍醐味です。演じている最中も「今日は客席がやわらかくてリアクションしてくださっているな」とわかるんです。同じ演目でもお客さまの反応は毎回違いますし、演じる私たちの呼吸もその時々で変わるから、同じ舞台は2度とありません。そこに魅力とやりがいを感じて、ここ4~5年は舞台を中心に活動しています。

10代、20代のときは自分の意見を言えなかった
スカウトをきっかけに高校生でこの世界に入って、最初は自分が何をしたいのかさえもわからないまま、無我夢中で進んできました。何がお芝居の正解かもわからないし、監督によってもやり方が変わるし、壁にぶつかったことは数えきれないほどあります。反面、何もわからなかったからこそ、求められるいろいろな演出をすべて受け入れて、それに柔軟に応えようと取り組んでいるうちに、気づいたらある程度の基礎力がついていた。今そんなふうに感じています。
年齢を重ねるにつれて演じる役柄も役割も広がって、30代に入ってからは脇を固める配役も増えてきました。私自身も変化していて、自分のやりたいことがクリアになってくるのと同時に、10、20代のときは監督や演出家の方にまったくといっていいほど自分の意見を言えなかったのが、最近は言えるようになってきたかなと思います。もともと自分に自信がないうえに失敗するのが怖かったんですが、間違ったら恥ずかしいという自意識を手放したら「私はこう思いますがどうでしょうか」と気負わず伝えられるようになりました。
読書と落語という趣味が開いた仕事の扉
生のお芝居という点で私は舞台により強く惹かれるので、今後も舞台を中心に演じ続けて、場数を踏んで、もっともっと力をつけていきたいですね。それからここ2、3年は読書と落語という長年の趣味がきっかけになって、新聞などで書評をしたり、雑誌に連載したり、テレビの落語番組の案内役を務めたりと、お芝居以外の仕事にチャレンジする機会もいただけるようになりました。そちらの分野もさらに深めて、仕事の幅を広げていけたらいいなという希望ももっています。
演じること、読むこと、書くこと、落語を聴くこと、すべてが私にとって生きる糧で、仕事もどれか1つが欠けると成り立ちません。セリフとト書きしかない台本から登場人物の心情を読み取ろうとするとき、読書が与えてくれた想像力が助けになったり、書評やエッセイを書くときはマクラ・本題・オチという落語の構成を意識したり、噺家さんの仕草や表情からお芝居のヒントをもらったり、すべてつながっているんです。普段は言いたいことがあっても胸にしまっておく性格なので、書くことで自分の弱い部分やモヤモヤを浄化できているという効果もあるかもしれません(笑)
表現することが好き 人の喜ぶ顔を見るのが好き
これまでに何度か、「私はこのまま女優を続けていっていいのかな」と迷ったことがあります。それでもやってみようと思えたのは、表現することが心の底から好きだから。そして、誰かが喜んでくれる顔を見たいからです。家族、友だち、お世話になった方々、ファンのみなさん、お客さま…人を喜ばせたいという思いは私の最大のモチベーションになっていて、「誰かがきっと見て喜んでくれる」と思うと、疲れていてもどこからかエネルギーが湧いてくるんですよ。
16歳で初めてお芝居に挑んだとき、本当にできないことが多すぎて、悔しくて「自分の手で何かをつかめるようになりたい」と強く思いました。あれから16年、たくさんの素敵な方々や作品に出会えて、1人ではたどり着けなかった場所に立つことができています。この先も素晴らしい出会いや面白い経験が待っていると思うから、1番の目標は長く続けることです。常に好奇心をもって新しいことにチャレンジし、女優としても人としても成長していきたいと思っています。
文/水元真紀 写真/中西祐介
取材協力/落畑雄久(昭62経)

1990年埼玉県生まれ。2013年立教大学現代心理学部映像身体学科卒業。2006年デビュー。近年の舞台出演作品に『アーリントン』『更地』『エゴ・サーチ』『羽世保スウィングボーイズ』『血の婚礼』など。NHK『とっておき!朝から笑タイム』案内役、サンデー毎日『遠回りの読書』執筆、各種書評などでも活動中。舞台『セトウツミ』(2023/5/27 ~、東京芸術劇場(池袋)、他)に出演予定。