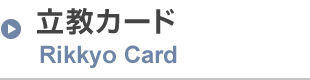Alumni Special Interview
研究室を訪ねて
コミュニティ福祉学部 福祉学科 教授 湯澤直美先生

コミュニティ福祉学部 福祉学科教授。1985年日本社会事業大学社会福祉学部児童福祉学科を卒業。社会福祉法人で勤務の傍ら、立教大学大学院社会学研究科に進学し、95年3月、社会学専攻を修了。日本社会事業大学社会福祉学部実習講師を経て、98年より立教大学コミュニティ福祉学部にて勤務。2022年4月、同学部学部長に就任。
コミュニティ福祉学部長の湯澤直美教授は、福祉の現場で働きながら、社会人として立教の社会学研究科社会学専攻の修士課程を修了され、他大学院で博士号を取得。在学中の思い出や現在の研究などについて伺いました。
●社会福祉の現場で働き 再び学びたくて立教へ
社会福祉を学び、とにかく現場で働きたいということは高校生のころから決めていました。貧困や暴力を身近に感じ、そのような問題をどうしたら克服できるのかを学びたくて、社会福祉系の学部に進学しました。卒業後に児童養護施設や母子生活支援施設で働きながら、貧困や暴力、虐待などの現実に日々直面しました。しかし、これらの事象は、1980年代にはまだ社会問題として注目されていなかったんです。「なぜ社会はこれらの問題を放置しているのだろうか」という憤りが常にありました。そこで、今一度社会福祉について学び直し、社会に発信していきたい、という思いから立教の社会学研究科に進学したんです。10年間、福祉の現場で働いた最後の2年に当たります。
なぜ立教だったのかというと、立教の名誉教授になられた庄司洋子先生のもとで学びたかったからです。先生は、立教に赴任なさる前には、私の学んでいた大学の教員をなさっており、卒論も庄司先生に見ていただいたんですね。社会人になってからも論文などを発表していたんですが、その際も先生にアドバイスをいただきました。その後、庄司先生が立教の社会学部の教員になられ大学院も担当なさるということを知り、「さらに学びを深めたい」という一心で社会学研究科を志したんです。
当時は母子生活支援施設という、シングルマザーの方が暮らす施設に勤めていて、フルに働きながら大学院に通う生活でした。宿直明けの日に授業を受けたり有休休暇を組み合わせたりして通いましたが、若くて体力があったから可能だったんでしょうね。日本社会学会での研究発表をはじめ、様々な経験ができました。大学院では、“スーパートレーニングゼミ”も思い出深いです。同じ社会学研究科の木下康仁先生(昭51社)のゼミと合同で、それぞれの学生が研究を発表しながら討議し、豊富な助言をいただける刺激的な時間でした。時間的にはハードでしたが、学生が相互に切磋琢磨する環境のもとで、真摯に研究に向き合う基本姿勢や研究の醍醐味を教わった気がします。
現在、庄司先生とは研究だけでなく、『学生支援ハウス ようこそ』という、家族と離れて暮らさざるを得ない若者の高卒後の就学を支援するNPO法人の運営を一緒に行なわせていただいたり、あれこれと相談にも乗っていただいたりしています。人生の恩師といえる存在です。
●“見ようとしなければ 見えないもの”を 見る力を養う大切さ
私の研究のフレームワークは、社会福祉の制度・政策にジェンダーやフェミニズムの視角からアプローチするというものです。具体的には、ジェンダーに基づく暴力や性的搾取、ジェンダー化された貧困、マイノリティ家族への差別などをテーマとして、その実態の可視化と克服のための方策を研究しています。被害や困難の解消にとどまらず、これらの問題が生み出される構造を射程にして、社会福祉学がどのような貢献ができるのかを考えたいと思っています。
また、研究と同時に、社会に対するアクション、つまり、ソーシャルアクションが重要だと考えてきまして、2013年に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が制定されるにあたっては、若者たちと市民運動に取り組みました。若者と話していると「社会が変えられると思えない」という声をよく聞きます。だからこそ、若者の声を聴き、若者とともに歩み、つながりのなかで社会はよりよくしていけるという確信を、次の世代に伝えなければいけない、と思っています。
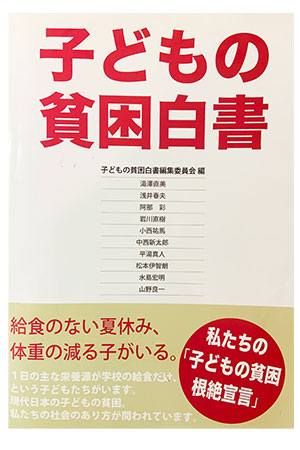
社会福祉って介護などのイメージが強いのですが、実はソーシャルワーカーというのは社会正義の実現や社会変革を担う大きな使命がある、というのが国際的な認識なんです。日本ではまだまだそういう認識が浸透していません。そこで、教員自ら社会に働きかけて変革が実現していく過程を体感し、学生にリアルな変化を語っていきたいと思っています。今年に入り、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が国会で成立したことも、ホットな話題です。
立教大学の教員になったのが1998年、ちょうどコミュニティ福祉学部が設立されたタイミングでした。受け持った授業の中でも、「ジェンダー論」は反響が大きかったですね。立教の教員になってからの25年間で、ダイバーシティとかLGBTQなどの言葉が知られるようになったように、ジェンダー問題に対する社会の意識や認知度は大きく変わりました。関心をもつ学生も増えました。しかし、ジェンダー平等が進んだかというと、根っこの部分で問題は深刻化していると感じています。ネットやSNSを介した性の商品化や性的搾取はむしろひどくなっており、セクシュアリティの侵害を通して女性を劣位に置く構造が強化されています。
授業では、性差別を感じた経験は一度もない、女性も強くなった、という声をよく聞きます。そこで、交通事故の逸失利益が賃金をもとに算定されると、被害者が子どもであっても男女で受取額に差が生じることなど、身近なことから気づきを得る機会をもっています。今まで当たり前に生きてきた社会の中に実は差別が潜んでいることや、差別を差別と思わせないような社会の仕組みがあることに気づいていくと、学生の学びの姿勢がどんどん変化していきますね。学生にはいつも「見ようとしなければ見えないものを見る力をつけていこう」と言ってるんです。これはつまり、“意思を発動する”ということ。それによって今まで見えなかったものが見えたら、その現状を変えるために学ぼうとする意志に転換されていきます。
教育ってあるひとつの眼鏡をかけるという行為でもあると思うんです。そこで集積された知識をもう一度批判的にとらえて、不要なものを学び落とす、これを“アン・ラーン”と呼びますが、いったん眼鏡を自分の意思で外してみて、そこから見えるものは何なのかをあらためて考え直す。その経験を、さまざまに提供したいと思っています。そしてそこから見える理不尽な現実を、自分だけの問題として捉えず、社会的な文脈のなかで捉え返してほしい。1人ひとりの声を時代の証言として受け止め合うこと。そこから、必ず世の中を変えられる、と。
●学生と教員、相互のリスペクトが理想のキャンパスを生む
私は22年4月から学部長を拝命しました。コミュニティ福祉学部は「いのちの尊厳のために」という理念を掲げているんですが、それを実現するにはまず教員が学生を尊敬できるか、が問われていると思うんです。それには学生の意見を傾聴し対話することが大切だと思っています。そのうえで伝統を尊重しながらも革新に挑み、教育と研究を両輪として発展させることで、理想的なキャンパスを具現化したいと考えています。学部創設当初は、新入生ガイダンスの際、教員や事務職員だけでなく、清掃や警備を担ってくれる業者の皆さんをお招きし、1年生全員にきちんと紹介していました。キャンパスに関わるすべての方々に思いを馳せられるようなホスピタリティーを大切にすることの重要性を初年次に感じたことは、今でも鮮明に覚えています。コロナ禍が落ち着いたら、ぜひ復活させたいです。