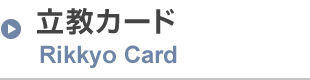Alumni Special Interview
研究室を訪ねて
外国語教育研究センター 関 未玲先生
外国語教育研究センターの関未玲准教授は、1991年に文学部フランス文学科に入学された校友です。以来、フランス留学で経験を重ね、2016年から4年間、愛知大学経営学部に赴任されていた期間を除き、一貫して立教でフランス語の教育に携わってこられました
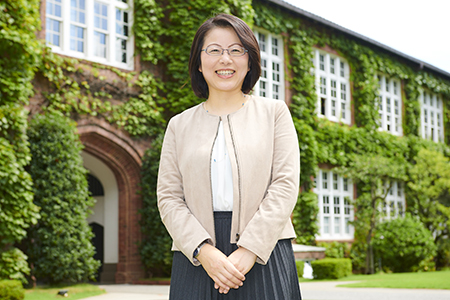
外国語教育研究センター 准教授 1996年文学部フランス文学科卒業。二度のフランス留学を経て、2006年3月に立教大学文学研究科フランス文学専攻博士課程後期課程を修了し博士号を取得、2011年12月にパリ第3大学大学院にて博士号を取得。
●普通とは違う何かを求めてフランス文学の道へ
もともと海外とつながりのある仕事に就きたいという漠然とした思いがありました。両親が立教出身ということもあり、受験した当時、立教のフランス文学科には文芸誌に名前が出たり、新刊をどんどん出す先生がたくさんいらっしゃって、とても活気があるところだ、という話も聞いていました。大学では新しい世界に飛び込んでみたい、という思いもあって、文学部フランス文学科を選びました。当時は構造主義に代表されるようなフランスの哲学や思想がブームになっていたし、フランス映画を見る機会も多く、日々刺激的な学生生活でした。
入学前からフランス文学を特にたくさん読んでいた、というわけではなかったんですが、日本や英米文学とはちょっと違う観点から書かれているな、とは感じていました。フランスの自由な気風、さまざまなものに対して開かれているというマインドが、自分を変えてくれるかも、なんて思ったのかもしれません。あるいはメジャーではない文学に触れることで、今までとは違った、普通の人とは違う自分を探してみたい、というのが隠れた志望動機だったのかも。
私の専門はフランス文学ですが、当然フランス語という言語を学ぶことでもあります。言語学習は正直で、努力した分裏切らずに自分を助けてくれるし、習得すれば通訳や翻訳などの仕事にもつながります。もちろんサボれば自分を見捨てることになるわけで、自分の力を見せつけられる世界だと思うんです。そのことにワクワクしました。初めて触れたフランス哲学は今まで自分が思っていた“哲学のための哲学”と違って、人生哲学というか、自分がどう生きていくのかに肉薄したもので、自分の人生そのものとどう向き合っていくのかを考える機会を与えてもらった気がします。
●最初の留学は失敗!?でもそれが今につながる
初めてフランスに行ったのは大学2年で、パリを中心としたいわゆる観光旅行で大いに刺激を受けて帰ってきました。その後4年生のときに最初の留学をしました。ブルゴーニュ地方のディジョンという町だったんですが、想像と違い、地方都市なので演劇もやってないし映画館ではハリウッド映画ばかりでショックを受けました。結局、自分が思い描いていたのはパリの文化だったということと、自分の語学力のなさもあって、失敗したなという歯がゆさだけが残りました。今思えば、地方が悪いとかそういうことではもちろんなく、自分がフランスという国の多様性を受け入れていなかっただけなんですよね。そのあと「フランス語の勉強はもうやめようかな」と思ったこともありましたが、最後にもう一度、今度は絶対パリに留学して自分の行くべき道を確かめよう、と。結果、パリで自分の求めていた文化に触れられたことで、もう少し大学院で勉強を続けたいなという思いにつながりました。
大学院では指導教官だった前田英樹先生と宇野邦一先生に大変お世話になりました。2人とも高名なフランス文学者であり、宇野先生は哲学者でもあるんですが、ご自身の考えを押し付けることなく「あとは自分たちで考えなさい」というタイプで、教わったことがすべてではなく、その先を自分で開拓することこそが勉学だということを教わった気がします。


●フランス語を取り巻く環境は大きく変化している
私の専門はフランスの女性作家マルグリット・デュラスですが、最近ではそのデュラスの影響を受けた次の世代のフランス、あるいはフランス語圏の女性作家が活躍していて、彼女らと共に活動しているんです。以前のフランスは自国が1番で自尊心がとても高いというイメージでしたが、私が今接している若いフランス人はそんな感じは全くなくて「これからはさまざまなフランス語圏の国々と連帯しないといけない」という強い危機意識を持っているんです。
もともとフランスの旧植民地だったアフリカ諸国の経済的な連帯に始まり、カナダの中で唯一フランス語を公用語とするケベック州が加わり、フランス語圏の連帯が形成されていった経緯があります。そんな動きの中で文学も互いに刺激しあって生み出されています。そこではフランスが絶対的な存在ではなく、フランス語圏の一員で、相対的な存在である、という多様化した価値観が広がっています。
多様化した価値観を広げるというのは、まさに外国語教育研究センターの理念と同じです。私は現在フランス語の教員という立場ですが、学生にはできれば1年でフランス語をある程度マスターしてもらい、早くその先にあるフランスの魅力を知ってもらいたい、と思っています。単なる外国語センターではなく教育・研究という言葉がついていることの意義は「語学はあくまでツールでありファーストステップである」ということ。それを駆使して次のステップである文化交流まで進まないと意味がないと思うんですね。単なる語学教育だけでは、フランス語を学びたいという学生のニーズにマッチしていないと思います。フランス語に興味がある学生は、言葉自体よりもその言葉を使っている自分自身に興味があると感じます。フランス語を使って世界が開け、地球儀が今まで見ていたのと別の角度で見えてくる。多様な価値観を共有しながら自分がどう地球にアクセスしていくのか……それをうまくイメージするためのプロセスを示すのが、教員の使命なのだと思います。
もちろん学生それぞれの専門分野があってこその外国語教育なわけですが、その専門分野での夢を、言葉ができないから諦めるという時代ではないです。むしろ、夢を実現するために言葉をちょっと習って、それを骨格としてどんどん肉付けする、でいいと思います。個人的には、フランスの文化を吸収するだけでなく、身につけたフランス語やフランス文化というフィルターを通したうえで、日本の文化を発信する人材が多く育ってほしいと願っています。
取材/野岸 泰之 撮影/ 増元 幸司